
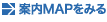
電車でお越しの場合・・・近鉄大阪線「法善寺」駅より東へ徒歩4分
お車でお越しの場合・・・外環状線(170号線)「柏原高校北」交差点を東へ
大阪府 柏原市はもちろん、大阪府(東大阪市、八尾市、藤井寺市、羽曳野市)、奈良県(大和高田市、香芝市、奈良市)、和歌山県などからも多数お越しいただいております。
![[腎臓専門医・糖尿病専門医・循環器専門医・人工透析]](../img/header_title_main.jpg)
柏原市・八尾市の糖尿病・心臓病・腎臓病・肥満症・高血圧
脂質異常症などの
生活習慣病および整形外科・リハビリを
専門医が診療します
慢性腎臓病(CKD)とは、腎障害や腎機能の低下が持続する疾患のことを言います。日本人のCKD患者数は約1330万人と推計されており成人の約8人に1人ということになります。CKDの原因は慢性糸球体腎炎といわれる腎臓そのものの病気のほか、糖尿病、高血圧、加齢などがあげられます。近年とくに糖尿病が原因でCKDになる方が多く注意が必要です。CKDは進行すると腎機能が廃絶し、透析療法や腎移植が必要となったり、心筋梗塞や脳梗塞などの心血管合併症を起こしやすくなります。しかし、病気が進行するまではほとんど自覚症状がありません。手遅れにならないためには、定期的に尿検査、血液検査を受けることをお勧めします。
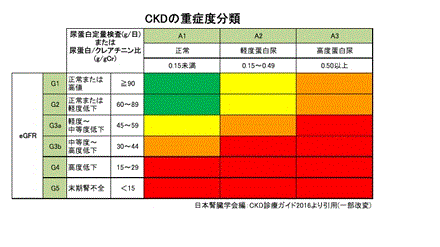
CKDの現状を把握しやすくするため日本腎臓学会からCKD重症度分類が提唱されています。腎機能が悪化したり、合併症を起こす危険度を緑〜赤の色で表しています。(赤に近づくほど危険度が高い)
日頃の検査データからご自身の重症度を評価してみてください。この表の横軸は尿検査でのタンパク量を表します。タンパク量の測定は1日蓄尿で測定する場合と1回の尿で推定値を測定する方法があります。縦軸は年齢、性別、血清クレアチニン値から換算式(*1)で求めたeGFR(推定糸球体ろ過率)という値です。
(*1)eGFR (mL/分/1.73 m²)= 194×血清Cr (mg/dL) −1.094×年齢(歳) −0.287
女性の場合には×0.739
eGFRだけでも現在の腎機能を知ることができます。eGFRは、腎障害がない状態では100程度の値ですので、現在の腎臓に残された能力をパーセンテージであらわしていると解釈するとわかりやすいと思います。
初期段階では慢性腎臓病(CKD)は自覚症状がほとんどありません。慢性腎臓病(CKD)が進行すると、タンパク尿(尿の泡立ちが消えない)、夜間頻尿、むくみ、貧血、倦怠感、食欲不振(食べても痩せる)、悪心、嘔吐、皮膚のかゆみ、血圧が高い、集中力の低下(尿毒症)、息切れなどが現れることがあります。

腎臓機能が低下すると、腎臓糸球体(血液を濾過するフィルター)が炎症したり傷つき、タンパク質が尿に漏れ出します。
腎臓機能が低下すると、ナトリウムを十分に排泄出来なくなり、抗利尿ホルモンの分泌が不足することで尿を濃縮する能力が低下して夜間の尿量が増加します。
腎臓機能が低下すると、水分と塩分のバランスが崩れ、体内の余分な水分が蓄積されることで足の甲やくるぶし、顔(朝目覚めたときに目や顔が腫れる)、全身のむくみが起こります。放置すると呼吸困難などを引き起こす可能性があります。
腎臓の機能が低下すると、エリスロポエチンの産生が減少し、赤血球の生成が低下することで貧血(腎性貧血)になります。腎性貧血になると、体中に酸素が十分に供給されなくなり倦怠感(疲れやすい)、動悸・息切れ、めまい、立ちくらみ、食欲不振(食べても痩せる)、むくみ、冷えやすさ、集中力の低下(尿毒症)などの症状が現れるます。
腎機の機能が低下すると、尿毒素が血液中に蓄積し皮膚の痒み受容体を刺激することで、皮膚のかゆみ(夜間に強い痒みを感じる)、皮膚の乾燥が起こります。
腎機の機能が低下すると、尿毒素が血液中に蓄積し脳にも影響を与えることで、集中力の低下や混乱、記憶力の低下などの症状が現れることがあります。
一度低下した腎機能は完全に元に戻ることはなく、徐々に腎機能が低下していきます。 まず、糖尿病や腎疾患など原因になった疾患の治療を行うことが重要です。その上に適切な生活様式の改善、食事療法、高血圧治療、貧血治療などで低下してしまった腎機能を維持できる可能性はあります。以下治療のポイントについて説明します。
喫煙やメタボリック症候群が慢性腎臓病に悪影響を及ぼすことが知られています。喫煙や暴飲暴食を避け適度な運動を心がけてください。水分摂取については、むくみがひどい場合を除き制限する必要はありません。脱水にならないよう水分摂取を行ってください。
腎機能の悪化や心臓血管疾患の発症を予防するため、過度な蛋白質や塩分の摂取に気をつけてください。CKDステージに応じて標準体重当たり0.6〜1.0g/日の蛋白制限が推奨されています。ただし、過度な蛋白制限は低栄養につながるため、管理栄養士と相談の上食事療法をすすめてください。塩分は特に高血圧を合併している場合は6g/日程度の制限が推奨されています。
高血圧は慢性腎臓病の進展のみならず、心臓血管疾患発症につながります。そのため130/80mmHg未満を目標とした降圧療法が推奨されています。降圧には禁煙、減塩、適度な運動などの生活食事習慣および服薬治療を行います。治療には腎保護効果のあるアンギオテンシン受容体拮抗薬(ARB)やカルシウム拮抗薬が使われることが多いです。
腎機能が廃絶すると生命を維持するために腎臓の機能を代替する治療(腎代替療法)を受ける必要があります。腎代替療法には透析療法と腎移植があります。 透析療法には、血液を体外の装置できれいにする血液透析と、ご自身の中の周りにある膜を利用し血液をきれいにする腹膜透析があります。それぞれの治療法には特徴がありますので、ライフスタイルに合わせて治療法を選ぶことができます。
下記ホームページをご参照ください。
ここでは、血液透析について説明します。
血液透析は、体外の人工の膜(ダイアライザー)に血液を通し老廃物や不要な水分を除去します。ダイアライザーの老廃物除去には2つの方法があります。一つは大きさの小さい老廃物を除去する、濃度差を利用した拡散という方法です。もう一つは比較的大きな老廃物を除去する、ろ過という方法です。
血液透析にはこの拡散と濾過を組み合わせることで色々な方法があります。
近年主流となりつつあるオンラインHDFは、核酸と大量の透析液を用いた濾過を組み合わせることで、小さな老廃物から大きな老廃物まで効率よく除去できます。
血液透析方法は、患者さんそれぞれの生活様式、体格にあわせて個別に決定します。ご自身にあった方法で血液透析を受けると、体調の良さが実感できるようになり、決してつらい治療法ではありません。
血液透析で十分な血液浄化を行うと、老廃物とともにわずかですがどうしてもアルブミンなどの栄養分も抜けてしまします。健康に血液透析治療を続けるためにはこの栄養分の漏出を補うべく十分な栄養摂取が大事になります。また塩分を多く摂ると体内に水分が貯留しやすくなり体重増加をきたしやすくなります。透析間の体重増加が多いと、時間あたりの除水量が増え心臓に負担がかかりますので、医師や管理栄養士と相談し個々のライフスタイルや病状にあった食事量、食事内容を決めることが大切です。
適度な運動により筋肉量を維持あるいは増加させることは、健康寿命を延ばすことに繋がります。透析直後を避ければ運動を行ってもかまいません。 ただし、透析患者さんは、心機能が低下している場合が多いため、医師や理学療法士と相談し個々の心臓の機能にあった運動量を決めることが大切です。
透析患者さんは腎臓でのカリウムやリンの排泄が著しく低下しているため、高カリウム血症や高リン血症をきたしやすくなります。 血中のカリウムが高くなると不整脈を起こしたり、心停止に至る場合もあります。高カリウム血症の予防のためには、生野菜や果物などカリウムを多く含む食品の過度な摂取をひかえる必要があります。また、消化管からカリウムを排泄する薬で治療する場合もあります。 血中のリンが高くなると、リンとカルシウムが結合し骨以外に石灰化(異所性石灰化)をおこしやすくなります。特に血管の石灰化は脳梗塞や心筋梗塞を起こしやすくなります。また、副甲状腺ホルモン(PTH)が高くなり、骨からカルシウムが失われもろくなります。リンは、たんぱく質や食品添加物に多く含まれます。特に加工食品に含有される食品添加物のリンは吸収されやすく過度な摂取は控えてください。たんぱく質摂取を控えると栄養不足になりがちなため、十分な栄養を摂取してなおリンが高い場合は積極的にリンを下げる薬を内服しましょう。 腎臓は腸管からカルシウムの吸収を促進するビタミンDを活性化させるため、透析患者さんではビタミンD不足になり、血中カルシウムが下がる傾向があります。血中カルシウムが下がると高リンと同じようにPTHが高くなり、骨が減少することになつながります。カルシウムが低い場合は、活性型ビタミンD製剤の内服や注射を行います。 カルシウムやリンを補正してもなおPTHが高い場合は、副甲状腺のカルシウム受容体に作用する薬剤の内服や注射で治療することもあります。
腎臓では骨髄に造血を促すエリスロポエチンというホルモンが分泌されます。透析患者さんはこの機能が低下しているため貧血をきたしやすくなります。 そのため透析患者さんは、エリスロポエチンの注射製剤を定期的に投与したり、エイスロポエチンの働きを助ける薬剤の内服を行います。体内の鉄分が不足している場合は、鉄含有製剤での鉄の補充を行います。
腎臓内科・人工透析センター長プロフィール
前野芳史