糖尿病の概要・原因・症状・診断について
糖尿病の概要
糖尿病は、血液中のブドウ糖(血糖)が慢性的に高い状態が続く疾患で、インスリン(血糖を下げるホルモン)の作用不足により引き起こされます。主に1型糖尿病(自己免疫や特発性が原因)と2型糖尿病(生活習慣との関連が強い)に分類されます。
糖尿病の原因・症状
- 糖尿病の原因
- ・食生活の乱れ ・運動不足 ・遺伝的要因 ・加齢やストレス ・自己免疫異常(1型)など
- 糖尿病の症状
- ・口渇(のどが渇く) ・多飲・多尿 ・体重減少 ・倦怠感(疲れやすさ・疲労感)・手足の痺れ・目のかすみ・皮膚の痒み・乾燥
糖尿病の診断
糖尿病の診断は、1回の検査結果だけでは確定せず、原則として同一の検査を別の日に再検査し、いずれも基準を満たすことで糖尿病と診断されます。ただし、多飲・多尿・体重減少などの典型的な症状があり、随時血糖値が200mg/dL以上の場合などは、1回の検査結果で診断が確定することもあります。
- 空腹時血糖値での診断
- ・空腹時血糖値≧126mg/dL
- 食事2時間血糖値(OGTT2時間値)での診断
- ・食事2時間血糖値(OGTT2時間値)≧200mg/dL
- 随時血糖値での診断
- ・随時血糖値≧200mg/dL
- HbA1cでの診断
- ・HbA1c≧6.5%
※HbA1cとは、直近1~2ヶ月の平均血糖値を反映する指標
|
血糖値・ HbA1c |
| 空腹時血糖値 |
≧126mg/dL |
| 食事2時間血糖値 |
≧200mg/dL |
| 随時血糖値 |
≧200mg/dL |
| HbA1c |
≧6.5% |
このページの先頭へ 
糖尿病の治療
糖尿病の治療は、食事療法、運動療法、薬物療法の3本柱があり、高すぎる血糖値を正常域まで低下させ、合併症を防ぐことを目的としています。
糖尿病の食事療法
食べてはいけないものはありませんが、自分に合った分量で、バランスのとれた食事にする必要があります。食事療法は糖尿病治療の基本となるものです。
糖尿病の運動療法
運動療法は食事療法と並んで重要な治療になります。筋肉を減らさず脂肪を減らし、健康的な体質改善をするとともに、カロリーを消費する事で直接的に血糖を下げることが重要です。また、運動によりインスリンの働きが良くなるといったメリットもあります。しかし、急な激しい運動は、病状によっては合併症を悪化させる場合もあるため、医師の判断による運動処方が必要です。
糖尿病の薬物療法
薬物療法には、飲み薬(経口血糖降下薬)による治療とインスリン・GLP-1受容体作動薬の自己注射療法の二つがあります。 使用薬剤の選択は、個人個人の体質や合併症の程度にあわせて千差万別です。
- SU薬(スルホニル尿素薬)
- ・主な作用:インスリン分泌促進 特徴:低血糖リスクあり
- ・主な薬剤一般名:グリメピリド・グリクラジド等
(製品名:アマリール錠・グリミクロン錠等)
- α-GI(α-グルコシダーゼ阻害薬)
- ・主な作用:糖吸収遅延 特徴:食後高血糖抑制
- ・主な薬剤一般名:ミグリトール・ボグリボース等
(製品名:セイブル錠・ベイスンOD錠等)
- ビグアナイド薬
- ・主な作用:糖新生抑制 特徴:体重増加少
- ・主な薬剤一般名:メトホルミン塩酸塩
(製品名:メトグルコ錠等)
- チアゾリジン薬
- ・主な作用:インスリン抵抗性改善 特徴:浮腫に注意
- ・主な薬剤一般名:ピオグリタゾン
(製品名:アクトス錠)
- DPP-4阻害薬
- ・主な作用:インクレチン分解抑制 特徴:食後高血糖抑制
- ・主な薬剤一般名:シタグリプチン・アログリプチン・リナグリプチン等
(製品名:ジャヌビア錠・ネシーナ錠・トラゼンタ錠等)
- GLP-1作動薬
- ・主な作用:インスリン分泌促進・食欲抑制
特徴:食後高血糖抑制・体重減少・注射・経口薬あり
- ・主な薬剤一般名:セマグルチド・チルゼパチド・デュラグルチド等
(製品名:ウゴービ皮下注・オゼンピック皮下注・リベルサス錠
トルリシティ皮下注・マンジャロ皮下注・ゼップバウンド皮下注等)
- SGLT2阻害薬
- ・主な作用:糖排泄促進 特徴:体重減少、心腎保護効果
- ・主な薬剤一般名:ダパグリフロジン・エンパグリフロジン等
(製品名:フォシーガ錠・ジャディアンス錠等)
- インスリン
- ・主な作用:血糖直接低下 特徴:注射製剤
・1型糖尿病にはインスリン療法が必須です。
必要に応じてSAPやインスリンポンプも使用する
※SAP:リアルタイムCGMを併用したインスリンポンプ療法
- ・超速効型インスリン
特徴:インスリン追加分泌(食後高血糖)用として立ち上がりが早い
作用発現時間:10~20分
最大作用時間:30分~1時間30分あるいは1~3時間
作用持続時間:3~5時間
注射タイミング:食直前
主な薬剤一般名:インスリン アスパルト・インスリン リスプロ等
(製品名:フィアスプ注・ノボラピッド注・ルムジェブ注等)
- ・速効型インスリン
特徴:インスリン追加分泌(食後高血糖)用、超速効型インスリンより立ち上がりは遅い
作用発現時間:30分~1時間
最大作用時間:1~3時間
作用持続時間:5~8時間
注射タイミング:食前30分
主な薬剤一般名:生合成ヒト中性インスリン・ヒトインスリン等
(製品名:ノボリンR注・ヒューマリンR注等)
- ・持効型溶解インスリン
特徴:インスリン基礎分泌用、作用持続時間は約24時間であり最大作用時間に明らかなピークはない
作用発現時間:1~2時間
最大作用時間:明らかなピークはない
作用持続時間:約24時間
注射タイミング:通常1日1回、毎日同じ時間(※アウィクリ注は1週間に1回、同じ曜日)
主な薬剤一般名:インスリン イコデク・インスリン デグルデク・インスリン グラルギン等
(製品名:アウィクリ注・トレシーバ注・ランタス注等)
- ・中間型インスリン
特徴:速効型インスリンにプロタミンを添加して結晶化させ、作用時間を長くさせたインスリン
作用発現時間:30分~3時間
最大作用時間:2~12時間
作用持続時間:18~24時間
注射タイミング:朝食前30分以内
主な薬剤一般名:生合成ヒトイソフェンインスリン・ヒトイソフェンインスリン等
(製品名:ノボリンN注・ヒューマリンN注等)
- ・混合型インスリン
特徴:インスリンの追加分泌を補う超速効型あるいは速効型製剤に一定量のプロタミンを加えたもの、あるいは中間型を組み合わせた製剤
作用持続時間:15~24時間
主な薬剤一般名:二相性プロタミン結晶性インスリンアスパルト・生合成ヒト二相性イソフェンインスリン等
(製品名:ノボラピッド30ミックス注・ノボリン30R注等)
- ・配合溶解インスリン
特徴:超速効型インスリンと持効型溶解インスリンを混合した製剤
作用発現時間:10~20分(Bolus画分)
最大作用時間:1~3時間(Bolus画分)
作用持続時間:>42時間(Basal画分)
注射タイミング:1日1回投与は毎日一定、1日2回投与は朝食直前と夕食直前
主な薬剤一般名:インスリン デグルデク/インスリン アスパルト
(製品名:ライゾデグ配合注)
このページの先頭へ 
糖尿病治療の日常生活での注意点
バランスのとれた食事 ・運動習慣(ウォーキングなど) ・薬の飲み忘れ防止 ・ストレス管理を行う。
このページの先頭へ 
当院での取り組み
白岩内科医院では、複数の日本糖尿病学会認定糖尿病専門医や指導医が、糖尿病に関する診療全般を包括的に担っています。さらに、国立病院機構大阪医療センターの加藤研医師が、1型糖尿病専門外来のために先進医療外来を担当し、先進的な治療にも対応しています。
また、管理栄養士、理学療法士、薬剤師、看護師などの多職種が連携し、食事指導や運動療法、フットケア、薬物管理など、患者さん一人ひとりに応じたサポートを継続的に提供しています。
このページの先頭へ 
引用・参考文献
下記ホームページも併せてご参照ください。
詳しい情報や最新情報などを閲覧することができます。

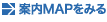
![[糖尿病専門医・1型糖尿病専門外来]](../img/header_title_main.jpg)